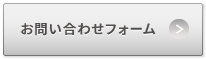1、2020(令和2)年の政局の関心事は衆議院解散の時期である。というのも、現衆議院議員の任期は2021(令和3)年10月であるが、解散権を実質上握っている内閣総理大臣(首相)安倍晋三氏の自民党総裁としての任期は同年9月であることから、今後の政治日程や後継者と目される人を含めた自民党内の動勢との兼ね合いで、マスコミや政治関係者の間で大きな話題になるからである。
2、衆議院の解散権は憲法上は内閣にあるが(憲法7条本文および3号、同69条)、内閣の一体性から内閣総理大臣には国務大臣である閣僚を罷免することができるので(同68条2項)、実質上、内閣総理大臣である首相が解散権を行使できることになる。実際、2005(平成17)年の小泉純一郎首相は、閣議で解散に賛成しなかった農水大臣を罷免して「郵政解散」を断行している。では、内閣総理大臣はいつでも好きな時に解散権を行使できるのであろうか。この点について、解散権の根拠を確認した上で、解散権の限界を検討することとする。
3、解散権の根拠については、憲法上、7条説と69条説等があるが、天皇の国事行為としての「衆議院を解散すること」の「助言と承認」を内閣がすることから7条説が通説となっている。司法においても、1957(昭和32)年の吉田内閣による「抜き打ち解散」で衆議院議員を失職した苫米地義三氏が、解散の無効を理由に議員の地位確認と議員歳費支払いを求めた訴訟において、最高裁大法廷は、4裁判官の意見が付されたものの、7条説を事実上承認したうえで、解散のような「極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為」は司法判断の対象とならないとして請求を斥けている。ちなみに、この「(純粋な)統治行為論」は、同時期に大法廷に回付されていた砂川事件における「(変形的な)統治行為論」の形成に中心的役割を果たした入江俊郎最高裁判事の主導によるものであるとされている(嘉多山宗「統治構造において司法権が果たすべき役割[第5回] 判例時報2385号128頁)。
4、では、解散権の限界はどのよう画されるのであろうか。この問題は、憲法学上、これまでの7条説的慣行を含めた実例や今後の実践をどのように規範的に位置づけるべきかという問題であり、これまで政治道徳、憲法上の習律ないしは法的要請などと言われてきたものである。この点、少し古く政治的なものではあるが、1952(昭和27)年6月17日に国会の両院放棄委員会が衆議院解散に関して勧告を出しており、それによると内閣の裁量解散可能説を支持するものであったが、同時に、内閣の裁量を「あらたに国民の総意を問う必要がありと客観的に判断されうる十分な理由がある場合」に限定するものであり、「解散は、いやしくも、内閣の恣意的判断によってなされることのないようにせねばならない」と念を押した上で、「衆議院が解散に関する決議を成立せしめた場合には、これを尊重し、憲法第7条により解散の助言と承認を行うがごとき慣例を樹立することが望まし」いとも述べられている(山本龍彦ほか「憲法判例から見る日本」第12章 日本の解散権は自由すぎる!? 258頁 日本評論社 2016年9月)。この点からすると、衆参同時選挙は余程のことでもない限り恣意的なものとなるであろう。
5、憲法と同時に施行された地方自治法にも憲法69条と同じ仕組みの規定があり、法178条によれば自治体の議会が長(知事または市町村長)の不信任の議決をしたときには、長は議会を解散することができるとされており、自治体の場合は首長がそのまま解散するが、国の場合には天皇の国事行為とされただけであり、憲法7条の国事行為として「憲法改正の公布」があるからと言って内閣が憲法改正をできないのと同様に、同条を根拠に内閣は衆議院解散をできないと言えなくもないが、実務慣行を前提とするとしても、やはり予算が否決されたとか重要法案を巡って国論が大きく分かれたときなど内閣不信任に匹敵するようなことがある場合に限られるべきであろうとする議論にはある意味説得力があるというべきである(片山善博「衆院解散の根拠」中国新聞 オピニオン 2017(平成29)年11月21日)。
6、内閣が恣意的に解散権を行使すると、参議院議員の半数改選選挙も3年に1回あることから、国民は選挙疲れで関心が薄れていくことも否めない。前回の2017(平成29)年10月22日の衆議院議員選挙当時、それまでの10年で当該選挙を含めて7回国政選挙が行われていることになるが、英国、ドイツは過去10年で3回、フランスは大統領・議会選が2回、米国は大統領・議会選は3回、議会中間選挙は2回の計5回に比べるといかにも多い感がある。日本が議院内閣制の範とする英国では、2011(平成23)年に首相が都合のいい時に解散権を行使するのを制限するために、議員の任期を5年に固定し、解散には下院議員の3分の2以上の賛成が要るようにしている(日本経済新聞 大機小機 2017(平成29)年10月7日)。もっとも、EU離脱をめぐり議会が混乱しているような場合は、「総選挙を12月に実施する」という新法を過半数で可決して総選挙に持ち込むという奇策もありうるのかもしれないが。ともあれ、安倍首相には、解散権の行使について安易に憲法改正の問題にもっていくことなく、解散権の原点に戻って考えていただきたいものである。