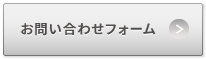天皇陛下の生前退位について
1、天皇陛下が、ビデオメッセージ「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」において、退位の意向をにじませられたのが、平成28年8月8日のことである。これに先立って、NHKによる「天皇陛下『生前退位』の意向」のスクープが報じられていたが、当初、宮内庁はこれを否定するなど不自然な経緯はあったものの、天皇陛下の「おことば」は、「現行の皇室制度に具体的に触れることは控え」、「個人として、これまでに考えて来たことを話したい」とお断りなっていることから、現行憲法上の「天皇」という立場にもとづく制約にご配慮されたものであった。この「おことば」を契機として、現行憲法上の疑義からか、「天皇の公務の負担軽減等に関する」という冠称の「有識者会議」が発足し、実質上、天皇の退位をメインテーマとする議論が始まった。天皇の退位に反対意見を述べる有識者も一定数いたものの、衆議院議長大島理森氏のとりまとめにより、皇室典範の付則にその根拠規定を設けることで、平成29年6月9日、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が成立し、天皇陛下が生前退位されることになった。しかし、「おことば」の内容から考えて、あのビデオメッセージまでの過程において、天皇陛下の周辺でかなりのやりとりがあったことは想像に難くなく、実際、天皇陛下の退位の意向については、「NHKなどの報道によれば、2010年7月22日の参与会議で、天皇は退位の意向を表明。しかし、側近は『これまで象徴としてなされてきたことは国民は皆、分かっています。公務に代役を立てるなどして形だけの天皇となられても異を唱える者はいません』と翻意を促し、『違うんだ』と否定する明仁天皇と激論になったという。」(吉田裕・瀬畑源・河西秀哉編 「平成の天皇制とは何かー制度と個人のはざまで」179頁、180頁 岩波書店 2017年7月)とされており、天皇陛下はかねてより生前退位の意向を持っておられたようである。
2、現行憲法には、天皇の生前退位についての規定はなく、皇室典範において、皇嗣の即位は天皇が崩じたときとされているだけである(皇室典範4条)。また、現行憲法上、天皇は、内閣の助言と承認による国事行為のみを行うことができるとされていることから(憲法7条1号ないし10号)、天皇の発意で、法律と同位の皇室典範を改正することはできないものである。天皇陛下も、このようなことは十分ご承知の上で、あの「おことば」を述べられていると思われる。ではなぜ、天皇陛下は、あのビデオメッセージによる「おことば」を国民に対して述べられたのであろうか。思うに、これまで天皇陛下は、国民主権に立脚した現行憲法における「象徴天皇」の在り方についてつきつめて考えてこられ、その上で行動されてきているが、臨時代行や摂政では意味をなさない、象徴天皇ご自身だからこそ意味のある行動を今後も継続していくには、抗いようのない年齢的限界を感じられ、象徴天皇の自然な承継と皇室の安定的な行く末も考えた上で、あの「おことば」を述べられたのではないだろうか。これまで天皇陛下は、「傷つき苦しむ国民を慰藉すること、敵も味方も含めて先の大戦の戦没者たちの霊を弔うこと」を、象徴天皇としての本務と考えられ、それを全身全霊で行動に移されてきたものと思われる(内田樹「街場の天皇論」67頁 東洋経済新報社 2017.10参照)。象徴天皇としての行為には、国事行為としてのさまざまな認証行為などのほか、国会開会式へのお出ましと「お言葉」、全国植樹祭、国民体育大会、全国豊かな海づくり大会など毎年3回の地方訪問や外国ご訪問などの公的行為、さらに、その他の行為として皇室祭祀などがある(皇室祭祀などの概略については、高森明勅「天皇『生前退位』の真実」122頁以下参照 幻冬舎新書2016.10)。天皇陛下は、これらの日程を割いて、被災地のお見舞い(これまで57回)や、中国との国交正常化20年の節目に中国政府の招きで訪中されたほか(平成4年)、硫黄島(平成6年)、サイパン島(平成17年)、ペリリュー島(平成27年)、フィリピン(平成28年)などの多数の戦死者を出した戦跡へ慰霊の旅をされ、戦死者に深い思いをはせてこられており、年齢的にもかなりの無理をしてこられたことは間違いのないことであろう。被災地での慰問において、膝をつかれて、被災者にねぎらいの言葉をかけられるお姿や、戦没者慰霊の旅に際して深く頭を下げられるお姿には、ひとかたならぬ感動を覚えるものがある。だからこそ、国民の多くが天皇陛下のあの「おことば」に共感したのである。現行憲法上の象徴天皇と国民主権との関係においても、天皇陛下の象徴としての行動の実践によって、時間をかけてゆっくりと調和させていかれたものであり、そのことによって、象徴天皇としての天皇陛下が、日本国民の心の中にしっかりと定着していったものと思われる。天皇陛下の今回の「おことば」のような「公的行為」の憲法上の位置づけについて、憲法学者がいろいろ論じているが、もともとGHQの草案においても明確な定義づけのなかった「象徴天皇」について、昭和天皇の強い意志を引き継がれ、全身全霊で国民に対しての内面化に務めてこられており、その心情が国民にしっかりと定着している以上、あまり意味を持つ議論とも思えない。
3、現在の国会の議席数の情勢からすると、国会による憲法改正の発議が十分に考えられるが、仮にそのようになっても、天皇の象徴としての地位については、現状のまま維持されるべきである。この点、自民党の改憲草案では、天皇は「象徴」とともに「国家元首」とされ、国事行為も「内閣の進言」しか必要とされていないなど、解釈によっては、なんらかの国政に関する権能をも持ちうるようなものになっている。しかしながら、天皇陛下は、これまで、現行憲法の平和主義を尊重され、被災者や戦没者なども含め、国民にできるだけ身近に寄り添ってこられ、国民の心の中にもそのような象徴として定着しているものであるから、それをあえて国家元首にする必要まではないのではないか。というのも、天皇陛下は、戦前の「帝王学」とは大きく異なり、現行憲法の理念に即した教育をうけてこられており、天皇陛下の考え方に影響があったとすれば、青年時の英語教師であった、絶対平和主義で知られるキリスト友会(クエーカー)のフレンド奉仕団で働いていたエリザベス・グレイ・ヴァイニング夫人(吉田裕ほか編 前掲書9頁)や、イギリス生まれの日本文学研究者レジナルド・ブライス氏(「NHKスペシャル」取材班 「日本人と象徴天皇」97頁 新潮新書 2017.12)の影響が考えられる。とりわけ、ブライス氏は、4年間だったヴァイニング夫人に比べ、18年もの長期にわたっており、その影響は大きかったと考えられる。ブライス氏の秘書であった岩村智恵子氏が、興味深いエピソードを紹介している。それは、「皇太子殿下が中学1年か2年のとき、一対一で御進講しているときに、テーブルから鉛筆が落ちたことがあったんですって。そのとき、誰が拾うか、ということになって、皇太子殿下は『近い方の人が拾えば良いと思います』っておっしゃった。それで、先生は、『じゃあメジャーもってきましょうか』っていうわけ。でもね、続けて『これはねあなたが拾うべきですよ、なぜならばあなたは皇太子だから』と言ったそうです。」(「NHKスペシャル」取材班 前掲書 96頁ないし100頁)というものであるが、その後の天皇陛下の被災地慰問における行動に結びついているようにも思われる。それはともかく、自民党の改憲草案のメインは現行憲法9条にあることは間違いなく、現在の日本をとりまく国際情勢を踏まえて、どのような可憲ないし改憲が考えられるか慎重に検討されなければならないが、いずれにしても平和主義の精神は引き継がれなければならないということである。なぜなら、天皇陛下が、戦争被害を受けた内外の人々に対する反省と慰藉の言葉をこれまで繰り返し語られ、鎮魂のための旅を続けてこられたのは、象徴天皇として、現行憲法の擁護を暗に実践してこられたことになるからである(内田 前掲書38頁参照)。
4、天皇陛下は、皇太子時代に、最初の大きな試練をうけられている。それは、昭和50年、沖縄県で本土復帰を記念した海洋博覧会が開かれたとき、昭和天皇の名代として、初めて沖縄に行かれたときである。皇室に対する沖縄の感情は複雑であり、とりわけ、天皇の名の下に戦われた太平洋戦争で、唯一の大規模な地上戦が行われ、県民の4人に1人が犠牲となった歴史など、割り切れない気持ちがわだかまっていた。当時、沖縄文化について進講した沖縄文化研究者外間守善氏のメモには、「『何が起きるかわかりませんので、くれぐれもお気を付けられるように』と申し上げました。殿下は、『私は何が起きても受けます』と強いご覚悟でした」と記されている。実際、皇太子夫妻が「ひめゆり学徒隊」の慰霊碑に献花を行い、案内役のひめゆり同窓会会長から説明を聞き始めた時、訪問に反対する地元沖縄の活動家の青年が火炎瓶を投げつけたのだ。その決定的瞬間を撮影した、当時、読売新聞の新人報道カメラマンだった山城博明氏は、同じ沖縄県民として「県民の怒り」を捉えられたと自負したが、それ以上に印象に残ったのが、火炎瓶の先にいた皇太子の表情だったという。それは、「汗がたらたらなんですよ。この辺からもう流れ落ちてるんですよね。実際現場で直に見てね、汗を流して業務を遂行している姿を見たら、沖縄に関して関心を持たれているということはすぐわかりました」(「NHKスペシャル」取材班 前掲書 126頁ないし130頁)というものである。このように、天皇陛下は、皇太子の頃から、相当の覚悟で真摯に沖縄と向き合ってこられたものである。また、天皇陛下は、「学習院に育ち、自由といふものについても、人生の楽しみがどのやうなものかも知っていらっしゃる。」ものであるが、即位されたことについて、「日本国憲法には、皇位は世襲のものであり、また、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であると定められています。私は、この運命を受け入れ、象徴としての望ましい在り方を求めていくよう努めています。したがって、皇位以外の人生や皇位にあっては享受できない自由は望んでいません」(平成6年6月4日)と、後年、明言されている(高森 前掲書86頁、87頁)。このように自由を断念するという覚悟の上で、これまで国民に寄り添いながら全身全霊で象徴としての務めを全うしてこられたものである。その天皇陛下の「生前退位」の意向のスクープが、NHKの夜7時のニュースで報じられたのが平成28年7月10日の参議院議員選挙の3日後の7月13日というのは、単なる偶然なのだろうか。この点については、安倍政権が改憲に向かって加速するはずの選挙結果に対する天皇陛下からのメッセージと読む識者もおり、実際、フランスの「ル・モンド」紙は、「改憲を牽制する動き」だと解釈している(内田 前掲書65頁参照)。その真相はわからない。いろいろな見方はあるが、ここまで踏み込んで言及したものが一部の書籍等に限られているのは、不必要な憲法上の疑義が生じるのを避けるためであろうか。いずれにしても、すでに国民に定着した象徴天皇や現行憲法の平和主義を擁護するために、もっと発言していくべきである。
5, 最後に、前記3、でも引用した「NHKスペシャル」取材班による新潮新書「日本人と象徴天皇」について少し述べておかなければならない。この新書は、きわめて綿密かつ慎重な取材によるもので、その内容はかなり史実に近いものではないだろうか。この中で、昭和天皇とマッカーサーとの会見や書簡のやりとり(同書71頁)、昭和天皇のリアリズム(同書117頁)には興味深いものがあるが、なにより衝撃を受けたのは、この書籍のもととなったNHKスペシャルの番組の企画者であったプロデューサー林新氏が、亡くなる8日前に病床で口述したという「あとがき」である。その冒頭には、「『天皇』を、僕は以前は否定していました。その正当性や根拠が論理や事実で語れないこと、そして日本のあらゆる組織の『忖度』による無責任体制は、天皇制に根本があると思っていたからです。でも今、日本の近現代史を見つめてきた一人として個人的な見解を言えば、『日本に天皇はむしろ必要なのではないか』という結論を出さざるを得ないと思います。」とある。私もその結論にはまさに同感である。世俗的な政治権力とは距離をおき、「祈り」という誰もが抗えない儀礼によって精神的支柱としての存在であり続けた天皇は、やはり日本国民にとってなくてはならないものであろう。しかし、その天皇の地位にあるということは、われわれには容易に想像できないもののようである。それは、「あとがき」の最後に、天皇陛下の即位の礼の取材中、車列の中の天皇の顔をすぐ側でまじまじと見たときの忘れられない印象が語られているからである。それは、いつも穏やかな天皇の顔が、氷のように冷えきった、あらゆる感情を排した、まるで「能面」のようだったとあるからである。そのとき、林氏は、「天皇であるが故の孤独そして深い懊悩」を感じたという。われわれには計り知れない孤独と懊悩と向き合いながら、ひとえに平和裡における国民の安寧と幸福を祈っておられる天皇陛下のお姿には、ただただ頭が下がり、尊敬するしかない動かしがたいなにものかがある。